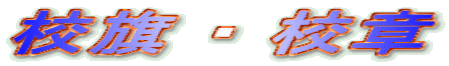
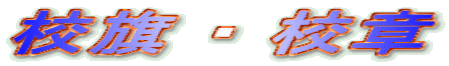
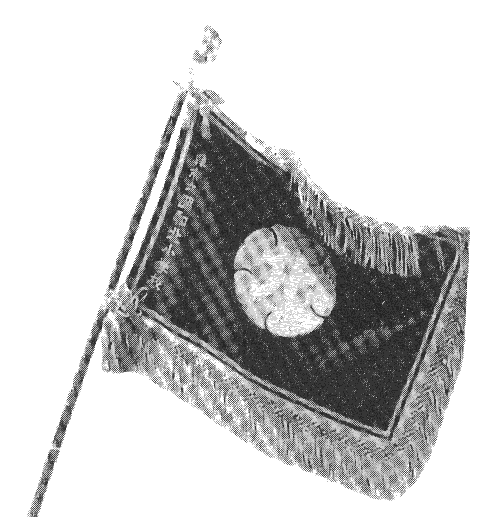 |
校章について この校章ですが、昭和北小学校が開校いたしました4月1日教育委員会より辞令を受けた者が職員室に集まり、北小の校章はどんなのがよいかいろいろ話し合いました。 それによると、この焼山の河岸とか学校をとりまく山の中にたくさん咲いている山ツバキは「呉市民の花」として呉市に住んでおられる方々に愛されているというところから校章は山ツバキにしようということになりました。 紀元前4世紀の哲人、荘園が「人間の寿命がどれだけ長いといっても8千年を春とし、8千年を秋とする大椿にくらべるとものの数ではない。」と述べています。衰えを知らない常緑の生命力から延寿の端木とされています。 また、日本書紀に火の神を生んで亡くなったイザナミノミコトは、熊野の有馬に葬られたが花のある時は花をもってまつる。この地方に繁茂するツバキの花が供えられたと考えられ、その精霊の働きによって、太陽神であるイザナミノミコトを復活させることを願いました。ツバキは太陽を招き豊作をもたらす精霊の花とされ、ツバキと繁殖の結びつきがあったようです。 さらに、正月の初釜にはツバキが茶花として用いられることはよく知っておられることと思います。このように、延寿の木、繁殖の木、初釜の茶花等とめでたいときに使われているツバキのように、「強く、明るく、美しく」育ち、たくましく羽ばたくことを願って本校の校訓として校章としました。 デザインについては、職員が考えたものを溝部 哲氏によって一層スッキリした形になりました。 |
| 校歌ができるまで(昭和53年度発行「つばき新聞」より 昭和52年9月10日に新校舎の落成式をあげた。落成式までに校歌と校章をつくりあげたいと考えていたが実現しなかった。各学校にそれぞれ校歌があるが、あらためて校歌とはいったい何だろうかと考え、広辞苑をくってみました。そこには「学校で校風を発揚するために特に制定した歌」とありました。 校章のツバキは「強く、明るく、美しく」を象徴し、校歌は校風を発揚ということから、作詞と作曲の観点をつぎのように考えました。 1 作詞について (1)昭和北小のめざす子ども像(強く、明るく、美しく)を入れる。 (2)ともに手をとって前進しようとする気持ち(感動、願いなど)が表れている。 (3)児童にわかりやすく、覚えやすく、親しみやすい詩であること。できれば口語体で・・・・・・。 (4)時代がたっても新鮮な感動がでるもの。 (5)詩の響きが美しいもの。 2 作曲について (1)全児童が歌いやすいもの。 (2)力強い感じのもの。 (3)リズミカルな曲であること。 以上に留意して 保護者、職員にお願いして、いろいろと作詞しましたが、第1回の卒業証書授与式には遂にまにあいませんでした。 忘れもしません。その年の修学旅行でバスが熊野町から矢野町へおりる浅田病院のあたりでした。ガイドさんが「さあ、みなさん昭和北小学校の校歌を合唱しましょう。」と元気づけた途端「まだ、できていないよ。」との返事に一瞬胸をつかれる思いがしました。何としてでも早くつくらねばと思うあいだに秋冬春夏が過ぎました。 書いては消し、書いては消して、みんなの力でつぎの校歌をつくりあげました。 |
|
| 作詞:北小PTA 作曲:山崎重一 | |
| 一 朝日に輝く 灰ヶ峰 見あげるひとみも さわやかに みんな手をとり 輪になって 強く 明るく 美しく 希望の光に 力わく |
二 波にきらめく 丘のいろ つばきのかざしも あざやかに みんな手をとり 輪になって 歴史をきずく 北小の 理想の光に 力わく |